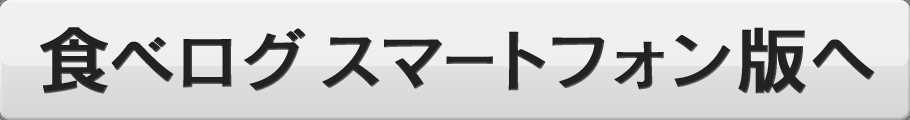皆さんこんにちは、今回も前回、前々回に引き続き、、私の趣味の果樹栽培関連の内容になります。
以前もこの場にて申し上げさせて頂きましたが、、今期の冬季シーズンはこれまでの冬季シーズンとは異なり農地内全体の大幅な改変がある関係上、、これまでとは比べ物にならない高頻度にて農地へやって来て色々と農作業に励んでおります。
今冬季シーズンはサルナシの育成開始に関する物事が多岐に渡っている関係で頻繁に果樹栽培関連の用事に勤しんでおりますが、、来年の冬季シーズンからは、、これまでと同様に年12か月の内の約3ヶ月程は、、果樹栽培の物事から離れてのんびりしようかと思っております。
では今回も、毎度の如く項目毎に分けてお話をさせて頂きたいと思います。
★1 シマサルナシも育成開始。
今回最初のお話は御題にも御座います様に、、つい最近になり「シマサルナシ」という名称の果樹の苗木を取り寄せて新規で植樹しました。
ではここで、、シマサルナシについて解説をさせて頂きたく思いますが、、、シマサルナシとは、、、私が昨年の11月から苗木を取り寄せて育成を開始しましたサルナシ(ベビーキウイ・ミニキウイ類も含む)、、有名な品種や商品名ですと「大実サルナシ・ファントム・エルダー・インパル・エメロード」等と言った主に果皮が緑色のサルナシや、、赤い果皮と赤い果肉になる「ガーネット・紫香」の様なサルナシ類とは種族上では近似種として扱われますが、、これらの園芸用に手が加えられたサルナシ類とは異なり、、世間一般に果実も苗も沢山出回っているキウイフルーツに、ある意味では最も近い、、または最も酷似している果樹なのです。
シマサルナシは今現在の日本では家庭での趣味栽培用途向けの苗は殆ど生産されておらず、、基本的には南関東以南(以西)の温暖な気候の地域、、、他の果樹にて指標としてよく用いられます「柑橘類全般・フェイジョアが1年中外に植えっ放しの露地栽培が可能な地域=暖地エリア」とされる地域の山奥の地域に自生している果樹でして、、、南関東以南の地域でも九州南部・沖縄県・和歌山県・三重県の伊勢志摩エリア、、、これらの日本国内の暖地エリアとされる地域の中でも特段に暖かい気候とされる地域に、より多く太古の昔から自然に見られる自然果樹なのです。
日本では「つる性の果樹」ですとブドウ類・キウイフルーツ類の2種のみが昔から商業価値の高い果樹として沢山の農家さんによって今現在も生産されており、ごく一部、、、同じつる性の果樹である「アケビ・ムベ」の2種もブドウとキウイに比べますと商業果樹としては賑やかでは有りませんが、、ごく一部、、国内に専門農家さんもおられ、アケビとムべはアマチュア向けの果樹苗の生産販売も盛んであり、、本当にここ数年でシマサルナシでない通常サルナシ類がようやく、、果実の味の良さ・育て易さ・栄養価の高さの3点に注目がされる様になって来たように私は感じるのですが、、シマサルナシに関しては今現在も絶滅危惧種に指定される程のマイナーさが際立つ果樹であるのです。
シマサルナシが商業用途に普及しなかった理由は明白であり、早い話が「キウイフルーツが有ればシマサルナシは要らない・出番はない、、つまり、作ってもキウイフルーツの方が可食部も大きいので売れない」という事が以前は際立っていましたが、、近年になり、キウイフルーツの実を食べる際に特定の体質の人が避けては通れない問題点としてキウイフルーツの果肉内にはアレルギー物質の「アクチニジン」という物質&成分が多量に含まれており、、キウイフルーツの味そのものがお好きな方であっても、、、アレルギー体質の方が食べますと口内と喉に激しい違和感や痒み、、唇付近に激しいかゆみや炎症が発生してしまう恐れがあるのに対し、、シマサルナシは見た目も内部もキウイフルーツに酷似している果実であるのにも係わらずキウイフルーツと同等の甘味や旨味が有る上にアクチニジンが殆ど含まれていない事も確認されており、、更にシマサルナシはキウイフルーツの様な果皮に毛が生えていなく、通常のサルナシ類と同様に軽く洗って包丁やナイフでのカットの必要もなくそのまま食べられる手軽さも有って、、今後、通常サルナシと同様に徐々にシマサルナシも普及して行く可能性が考えられる果樹なのです。
2023年の時点では三重県の和歌山県寄りの地域にてシマサルナシを普及させようと大々的に栽培と普及に向けて取り組んでおられる地域も実在し、私も是非、シマサルナシをやってみたいと考える様になり、つい先日、、シマサルナシ専用の特大フェンスの追加設置と苗木の用意も行い、農地内に植樹を完了しました次第です。
但し、、1点だけシマサルナシの育成に関する懸念点もあり、、私が用意したシマサルナシの苗木がオスの木かメスの木かが分らないという点が有るのです。
シマサルナシは大半の通常サルナシとは異なり、完全なる「雌雄異株」の果樹なので、私が用意して植えた苗がもし、、オスの木であったら永久に実を付ける事は無いと思われ、、メスの木でしたら近似種の通常サルナシの雌雄同株品種やサルナシのオスの木、キウイフルーツのオスの木が農地内に受粉樹として植えてありますので恐らく、、、今回の私が自農地内に植えたシマサルナシの木がメスの木であった場合は花が咲けば私の農地内にてシマサルナシの結実が見込めるかなと想像しておりますが、、こればかりは、、あと2~3年の年月が経過してみないと分からない物事であるのです。
シマサルナシは苗木の流通も殆ど無く、、基本的にはキウイフルーツの苗木の台木として使われる用途が大半であって、、今後、、余程の転機が発生して果樹苗の生産業者の方々が「今まではキウイの台木としてのみシマサルナシを作っていたが、、今はシマサルナシ本体の苗木として売れる」と認識しない限り、、、シマサルナシ単体での苗木の流通は望み薄であるのが実情であると思います。
因みに、私、、、愛知県岡崎市内の人気(ひとけ)も殆ど無く、付近に民家も全く無くて車通りも殆ど無い物凄い山奥の地域に、、、、天然自生のシマサルナシらしき植物が自生している場所を知っており、、もし今後、、私の農地内に植えたシマサルナシの苗木がオスの木であった場合、、この場所に脚立を車に積んで作業着姿で出向き、、自生シマサルナシの実が生っている9月末頃~10月中旬頃にこの場所に行って実が生っている=間違いなくメスの木である木から枝を採取して挿し木をしてシマサルナシのメスの木を自作して植えようかなとも考えております。
上記の山奥の場所は、、私が以前、天然自生のアケビの実を探して出掛けた際に、、つる性植物が生い茂る場所を探索していた所、、、地面より相当に高い場所に小さ目なキウイフルーツの実らしき果実が生っているつる性植物を発見、、何とか付近の木に登って、その小さ目なキウイフルーツの実らしきモノを数個採取してみた所、、果皮に毛が無い小さ目なキウイフルーツの様な見た目の果実であり、、、この時点では専門的な事は全く分かりませんでしたが、、今思えば、、これは愛知県岡崎市産の天然自生のシマサルナシでないかと考えております、、、今年の秋になったら、、再度、、その場所に行ってみようと思っております。
★2 テイカカズラ部分駆除。
さて次は、私の農地内には地主様のお父様が植樹されたとされる、、隣接農地との境界部に目隠し用に「ラカンマキ」の木がグリーンカーテンとして沢山植わっており、、、一部のラカンマキ密集地帯には毎年の高気温時期である夏場に、、とある困った自生植物が存在しておりまして、、今冬季シーズン中にこの困った植物の根元or中心部付近の主幹を剪定ハサミで切除して、、今後、、この植物が活発に生育しない様に対処しました。
その困った植物とは「テイカカズラ」という名称の植物です。
テイカカズラとは、、、一年中葉の落ちない常緑樹であり、、その上、、サルナシと同様につる性植物でありますので毎年の夏になると一部のラカンマキ植樹地帯から物凄い勢いでつるが延びて来ていたのです、、、。
私は毎年の夏に、その都度、、、自生テイカカズラが自生している箇所付近に植わっているアンズの木の枝につるが絡みつきだしたのを発見次第、、、その絡みついたつるのみを切除して対応していましたが、、今夏季シーズンからはサルナシとシマサルナシが植えてあるパーゴラやフェンス近くに自生しているテイカカズラは多大な問題があると考えまして、、、生い茂った自生テイカカズラの枝と葉を掻き分けて普段は余り露出していないテイカカズラの主幹部を発見し、、その主幹部を思い切りカットした事により、、、当然ながら幹がカットされ根からの栄養がカットした個所より上には送られて来なくなりましたので、、邪魔な自生テイカカズラの大半は自然と枯れて行きました。
しかしながら、、テイカカズラは一応は一般園芸商品としても苗木が売られており、、、常緑の上に病害虫の発生も殆ど無く、、秋~冬には葉が紅葉して美しく、、、適切に管理すれば一般家屋の目隠しや日差し除け、、オシャレなグリーンカーテンとしても活用出来る性質も持っており、、私も根から掘り起こしてでの完全駆除も最初は考えましたが、、、この自生テイカカズラのお陰でラカンマキでは完全に塞げない隣地からの目隠し効果の追加作用の利点を完全に失うのは惜しく感じましたので、、根元と根元付近の幹は残し、、今後、、また大きく育って果樹やパーゴラやフェンスに絡みそうな勢いになったら大幅切除を行って対処して行こうかなと考えております。
それにしても、、、元を辿ると何故、、この場所に天然自生のテイカカズラがたくさん自生しているのかが不思議に感じてしまうのですが、、、当然ながら、、地主様がラカンマキの根元に故意に植樹された木では有りませんので、、自然の植物の生態は不思議やなぁと感じました次第です。
あ、、それと、、つい先日に農地内の廃材置き場を綺麗に片づけて通常サルナシ育成専用の最後の機体となる「第5パーゴラ」も追加で設置しました。
今回は以上になります。